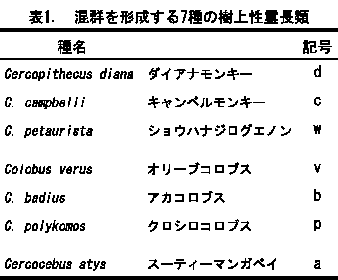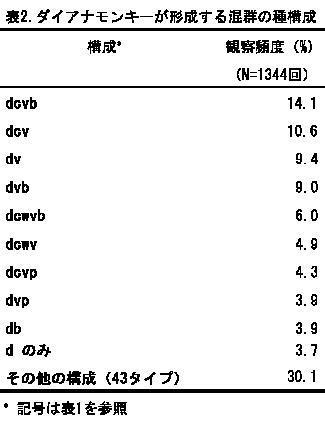- �쒷�ނ̍��Q�ɂ������ԊW
- �����@�O�i����E���E�l�ސi���_�j
- ���͂��߂�
�@�����̗쒷�ގ�́A�����I�ɑ���̗쒷�ނƂƂ��ɕ�炵�Ă���B�A�t���J�̔M�їтł́A�`���p���W�[��S�����Ȃǂ̗ސl�����܂߂āA����̃T�����������𗘗p���Đ�������B���틤���̒��ł��Ƃ��ɒ��ڂ����̂́A�َ�̌Q�ꂪ������������̌Q��̂悤�ɁA�ЂƂɏW�܂��Ĉꏏ�ɍ̐H������ړ������肷�鍬�Q�Ƃ������ۂł���B���Q��Ώۂɂ��������͂���܂ŁA�u�Ȃ����Q������̂��v�Ƃ������Q�̋@�\��T����̂��قƂ�ǂ������B���Q���`������s���̃��J�j�Y�����Ԃ̎Љ�W�ɂ��ẮA�قƂ�ǖ��炩�ɂ���Ă��Ȃ��B�{�ł́A���Q�̋@�\�ɏœ_�����Ă��������T�ς��A�R�[�g�W�{�A�[���̃^�C���������łV��̃I�i�K�U���ނ��`�����鍬�Q���Љ��B�Ƃ��Ɏ�̍\���Ƃ��̕ω��̓��Ԃɒ��ڂ������͂��s���A���Q�`���̋@�\�ɒ��ڂ����B
- ����ԋ����̐��Ԋw
�@�َ�̌Q�ꂪ�����W�܂��Ĉ�̌Q����`�����鍬�Q���ۂ́A�쒷�ނł̓A�t���J�Ɠ�Ă̔M�їтŕp�ɂɊώ@����Ă���B���Q�����̑����́A�u�����r�����ɔ����āA�Ȃ��߉��Ȉَ킪�Q������̂��v�Ƃ����₢���܂��������Ă���B�����r�����Ƃ́A�ގ����������𗘗p�����̊Ԃɂ͋��ʂ̎������߂����ċ����������N����A�ŏI�I�ɂ͂ǂ��炩�̎킪�p�������Ă��܂��������邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ƃ������[���ł���B���Q���`�����Ă����͌n���I�ɋ߉��Ő��ԓI�~�����ގ�������̂������̂ŁA���̃��[���ɔ����Ă���悤�Ɍ�����B�����̍��Q�����ł͂����ɌQ�W���Ԋw�I�ȋ�������A���̋����r�����̖������Q���ǂ̂悤�ɃN���A���Ă���̂��A���Q���ł̓j�b�`�V�t�g���N�����Ă���̂���₤�����������Ȃ��ꂽ�B
- �@�s�����Ԋw�̐����ȍ~�A�������߂��鋣�����Љ�\�����K�肷��Ƃ����Љ�Ԋw���A�쒷�ފw�̂ЂƂ̃X�^���_�[�h�ƂȂ����B�Љ�Ԋw�ł́A���Q�Ƃ����傫�ȌQ����`�����邱�Ƃ́A�̊Ԃ̋����ɂ��R�X�g�傷��͂��ł���A����ɂ�������炸���Q�`�����K���I�ł��邽�߂̗��v�͉����A�Ƃ����₢�����Ă���B�����łَ͈�̊Ԃ̋���������̊Ԃ̋����Ƃ܂����������ƍl���A�H�������̗ʂƕ��z������Q�̃O���[�v�T�C�Y�����肷��̂Ɠ����悤�ɁA���Q�`���ɂ��e����^����ƍl����ꂽ�B
- �����Q�̗��v����
�@���Q�����闘�v��������鉼���͑傫����̃^�C�v�ɕ����邱�Ƃ��ł���B
- �@���ɍ��Q�����邱�Ƃɂ���āA�ߐH�҂���葁������������A�ߐH�����m���������邱�Ƃ��ł���Ƃ����ΕߐH�҉����ł���B���Q�łَ͈�̌x���͂𗘗p���邱�Ƃɂ���āA�ߐH�҂̐ڋ߂𑁂��m�邱�Ƃ��ł���\��������B�R�[�g�W�{�A�[���A�^�C���������ł̓A�J�R���u�X���`���p���W�[�ɂ���̎�v�ȑΏۂł���B���Q���`�����Ă��Ȃ��A�J�R���u�X�ƃ_�C�A�i�����L�[�̌Q��Ƀ`���p���W�[�̉������v���C�o�b�N����ƁA�A�J�R���u�X���_�C�A�i�����L�[�ɋ߂Â��č��Q���`�����邱�Ƃ���A�A�J�R���u�X�͌x���s���̓��ӂȃ_�C�A�i�����L�[�ƍ��Q���`�����邱�ƂŁA�`���p���W�[�ɂ��ߐH������Ă��邱�Ƃ������ꂽ(No� and Bshary, 1997; Bshary and No�, 1997)�B
- �@���̉����́A���Q�����邱�Ƃɂ���āA�������I�ɍ̐H���ł���Ƃ����̐H�����������ł���B�H���̏ꏊ���悭�m���Ă����ƍ��Q������Ƃ����K�C�h������A���킪���p����������ɍ̐H�ꏊ��K��邱�Ƃ�����郊�j���[�A�������A�ΕߐH�Ґ헪�̗��v��g�ݍ��킹�āA����ɕߐH�҂ւ̌x�����܂����āA��葽���H�ׂ�ꂽ��A���댯�Ȓn��ō̐H�ł���Ƃ��������Ȃǂ�����B�P�j�A�̃J�J���K�ł̓A�J�I�U���ƃu���[�����L�[�����Q������(Cords, 1987)�B�A�J�I�U���͍��Q���`�����Ă���Ƃ��ɁA�d�v�x�̍������̂ɂ��ẮA���킪���ʂɗ��p����H����H�ׂ鎖�������B�܂��A�V����傫���A�J�I�U�����A�V����̏������u���[�����L�[�ɐϋɓI�ɋ߂Â��č��Q���`������X��������A�A�J�I�U�����u���[�����L�[���K�C�h�Ƃ��ė��p���Ă����Cords�͏q�ׂĂ���B
- �@��̋@�\�����͂ǂ����������O��Ƃ��āA�����̃R�X�g�ɂ�������炸���Q�`���ɂ���ăT�������v�Ă���̂ŁA���Q���i���I�ɓK���I�ȍs���Ƃ��Ďc���Ă����Ɛ�������B�ΕߐH�҉����ƍ̐H�����������͔r���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���Q�ɎQ�������\������̕ϓ��ɂ���āA�قȂ闘�v����\�����l������B
- ���^�C�̃I�i�K�U�����Q
�@�҂͐��A�t���J�A�R�[�g�W�{�A�[���̃^�C����������1993�N����1994�N�ɂ����āA���N�Ԃɂ킽���Ē������s�����B�����n���ɂ�8��̒��s���쒷�ނ��������A�`���p���W�[�������V�킪���Q�ɎQ������i�\�P�j�BCercopithecus��3��̂��ꂼ���Q���t�H�[�J����O���[�v�Ƃ��āA�̐H�s���ƌ`���������Q�̎�\�����L�^�����B3��Ƃ��ɍ��Q�������ɍ����A���Q�����炸�ɓ���O���[�v�����ł������Ԃ́A�������̂ł��ώ@���Ԃ�10%���x�ɂƂǂ܂����BCercopithecus���ǂ����̍��Q�����ł��A3��̍��Q���͑S���Ԃ�ʂ��Ă��ꂼ��50�����z���Ă����B
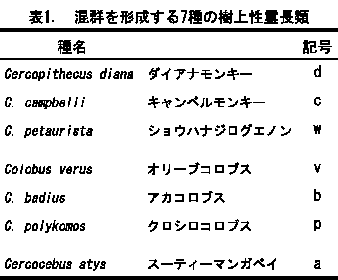
- �� �ΕߐH�ҍs��
�@�����n���ɐ�������I�i�K�U���ނ̕ߐH�҂́A�����Ƀq���E�iPanthera pardus�j�A���V�iStephanoaetus coronatus�j�A�`���p���W�[�iPan troglodytes�j��3��ł���(Zuberbuler et al., 1999)�B�A�J�R���u�X�̑`���p���W�[�헪����A�_�C�A�i�����L�[�ƃA�J�R���u�X�̍��Q�͋@�\�I�ɐ����ł��邪�A�`���p���W�[�̓A�J�R���u�X������I��I�Ɏ����̂�(Boesch, 1994)�A���̃T���ɂ͕ߐH���Ƃ��ċ��Ђł͂Ȃ��B�q���E�ƃ��V�ɑ��ẮA���ׂĂ̎킪�p�ɂɌx�������邪�ACercopithecus���̓q���E�ƃ��V�ɑ��āA���ꂼ��ʂ̉����\�����������x�����������Ă���(Zuberbuler et al., 1997)�B���Q���`�����邱�ƂŁA�َ�̌x�����𗘗p���Ă���̂�������Ȃ��B�������A�q���E��ҋחނ̕ߐH�����ǂꂭ�炢�Ȃ̂��A�ΕߐH�Ґ헪�Ƃ��Ĉَ�̌x�����̗��p���ǂ̂��炢�L���Ȃ̂��ɂ��Ă͂܂���������Ă��Ȃ��B
- �� �̐H�s��
�@�̐H��������������������̂́A�H���̏d�����傫����ǂ����̍��Q�̏ꍇ�ł���BCercopithecus����3��͏W�����z������ʎ�����v�ȐH���Ƃ���B�A�J�R���u�X�͉ʎ����(Wachter et al., 1997)�A�N���V���R���u�X�͉ʎ����q�������̐H���邪(McGraw, 1998)�AColobus���̎�v�ȐH���͗t�A���Ɏ�t�ł���B�X�[�e�B�[�}���K�x�C�͒n�㐫�������n�ʂɂ����Ă����q����ɍ̐H����ƍl�����Ă��邪�A��O�ł̌�����͂قƂ�ǂȂ��B
- �@Cercopithecus���̒��ł͉ʎ��Ɉˑ�����Ƃ������ʐ�������A�H���̏d�����傫���Ƃ����邪�ACercopithecus��Colobus�ACebus�̊Ԃ̐H���ɂ͈Ⴂ���傫���A�̐H�̌����������Q�̋@�\�ł���Ƃ͌��_�ł��Ȃ��B
- ����\���̕ϓ�
�@���Q�ɓo�ꂷ��V��̃O���[�v�́A���������藣�ꂽ����J��Ԃ��A���Q�͕ω����Â��Ă����B�_�C�A�i�����L�[���t�H�[�J���E�O���[�v �Ƃ��ĒǐՂ����ώ@�ł́A6��̃p�[�g�i�[�E�O���[�v���o������J��Ԃ��A�\�������Ԃ̌o�߂ƂƂ����X�ƕω������B�p�[�g�i�[��̍\�����ω����邽�тɐV������\���iAssociation�j�Ƃ��ċL�^����ƁA�_�C�A�i�����L�[��ǂ������Ă����Ƃ��Ɋώ@���ꂽ���Q�̎�\���̃p�^�[���́A�S����53��ނ������i�\2�j�B�_�C�A�i�����L�[�����Q����炸�ɁA1�킾���ł��邱�Ƃ͔��ɏ��Ȃ��A�ώ@���Ԃ�2.5���ɉ߂��Ȃ������B����ȊO�̎��Ԃ́A�����ƍ��Q������Ă������A�����\���ł���킯�ł͂Ȃ��A���@���G�e�B�[�ɕx���Q�̎�\���p�^�[���������玟�ւƕω������Ă����B
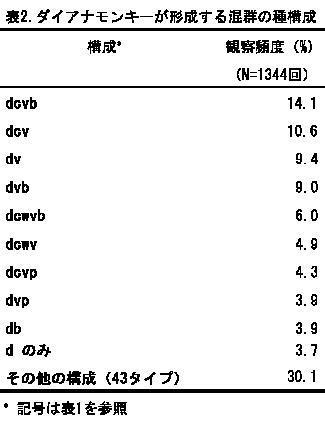
- �@��\���̃p�^�[�����ω�����Ƃ��ɁA���ٓI�ȍs������邱�Ƃ͊ώ@����Ȃ������B���Q�ł͎�Ԃ̒��ړI�ȑ��������ɏ��Ȃ��A�܂�ɋN����U���I���������ƁA�َ�Ԃł̎Љ�s���͂قƂ�nj����Ȃ��B�Ƃ��낪�A��\���̃p�^�[�����ω����钼�O�ɁA�̐H�̗ގ������ω����邱�Ƃ��ώ@���ꂽ�B���Q�̌`���╪�����N���钼�O�ɁA�_�C�A�i�����L�[�ƃL�����x�������L�[�̊Ԃł͍̐H�̗ގ������������A�V���E�n�i�W���O�G�m���Ƃ̊Ԃł͗ގ��������������B
- �@���Q�`���̋@�\������Ȃ�A���̗��v�邽�߂ɏ�ɓ��������o�[�ō��Q�����ق����悢�ƍl������B���Ƃ��A�ߐH�҂ɑ���h�q�͂���������Ȃ�A���ł��x���̓��ӂȎ�ƍ��Q�����Â��Ĕ����Ă����ق����悢�B����ɂ�������炸�A�^�C�̍��Q�ł�7�킪���������藣�ꂽ��A�o������J��Ԃ��A�ω����Â���B��\���̕ω��ƍ��Q���ێ�����s���̃��J�j�Y���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ł���A����̉ۑ�ł���B
- �������Ƌ���
�@�َ킪�����I�ɐ�������Ƃ������ۂ��A��̂����ʼn��߂��邱�Ƃ��ł���B
- �@�����F(1992)�́u��̑��l���v�Ɋւ���c�_�ɂ����āA�u�l�ߍ��݁v�v���Z�X�Ƃ��ċ����ł����̏�����l���鋣����z�肵�������ƁA�������\�ȃ��x���܂Ŏ킪�u�Ԉ����v�����v���Z�X���l���āA�����I�ȑ��݈ˑ��W��z�肵�������Ƃ�����̉��߂�Δ䂳���Ă���B
- �@���Q���@�\�����ɂ���Đ������邱�Ƃ́A���炩���ߋ����̃R�X�g��O��Ƃ��āA������N���A���č��Q���i���j�I�ɐ������邽�߂̗��v�����邱�Ƃ��ؖ�������@�ł���A������O�҂́u�l�ߍ��݁v�v���Z�X�Ƃ��Ă݂�����Ƌ��ʂ���B���Q�̓K���I�Ӌ`����������@�\�I�ȑ��ʂł���B����ŁA���Q�ł͂��݂��Ɏ��Ă��邯��Ǐ����Ⴄ�َ�ǂ������A�����I�ȑ��ݍ�p���J��Ԃ��ĂЂƂ̌Q����`�����Ă���ƍl����ƁA��҂̌����ŋ����𑨂��邱�ƂɂȂ邾�낤�B���̂Ƃ����Q�̃R�X�g�◘�v�ł͂Ȃ��A�����ŋN�����Ă��錻�ۂ̃��J�j�J���ȑ��ʂ��ڂ����������邱�ƂɂȂ�B���܂ł̍��Q�����͑O�҂̗���ɗ����̂��قƂ�ǂ��ׂĂł������B��҂̌����ŁA�߉��َ̈�ǂ����̋������l�@���邽�߂̗��_����@�_�͂قƂ�NJm�����Ă��Ȃ��B
- �@�^�C�̍��Q�ł͂V��̃T�������Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɍ��Q�ւ̏o������J��Ԃ��A���̌��ʁA�\���͏�ɕω�����B���Q�ɎQ������T���̍̐H�̗ގ��ƍ��ق̃_�C�i�~�N�X���A�̐H������َ�Ԃ̂����̃R�~���j�P�[�V�����Ƃ��Đ������Ă��āA���̃R�~���j�P�[�V�����̃A�E�g�v�b�g���\���̕ω��ł���ƍl���邱�Ƃɂ���āA���Q�łَ̈�Ԃ̎�ԊW�ɂ��āA���̎Љ������ɓ��ꂽ�������\�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B
- �Q�l����
- Boesch, C. 1994: Chimpanzees-red colobus monkeys: a predatory-prey system. Anim. Behav. 47, 1135-48.
- Bshary, R. & No�, R, 1997: Red colobus and Diana monkeys provide mutual protection against predators. Anim. Behav. 54, 1461-1474..
- Cords, M. 1987: Mixed-species association of Cercopithecus monkeys in the Kakamega Forest, Kenya. Univ. California Publications in Zoology 117, .
- �����F 1992: ���l�Ȑ����̋����@�\��T��. �u�V���[�Y �n�������n�Q ���܂��܂ȋ����\������Ԃ̑��l�ȑ��ݍ�p�v�i������V�ҁj, pp. 183-198. ���}��: ����.
- McGraw, W. S. 1998: Posture and support use of Old World monkeys (Cercopithecidae): The influence of foraging strategies, activity patterns, and the spatial distribution of preferred food items. Am. J. Primatol. 46, 229-250.
- No�, R. & Bshary, R 1997: The formation of red colobus-diana monkey associations under predation pressure from chimpanzees. Proc. R. Soc. Sci. Lond. 264, 253-259.
- Wachter, B., Schabel, M. & Noe, R. 1997: Diet overlap and polyspecific associations of red colobus and diana monkeys in the Tai National Park, Ivory Coast. Ethol. 103, 514-526.
- Zuberbuler, K., No�, R. & Seyfarth, R. M. 1997: Diana monkey long-distance calls: messages for conspecifics and predators. Anim. Behav. 53, 589-604.
- Zuberbuler, K., Jenny, D. & Bshary, R. 1999: The predator deterrence function of primate alarm calls. Ethol. 105, 477-490
���J�V���|�W�E���̃y�[�W�ɖ߂�