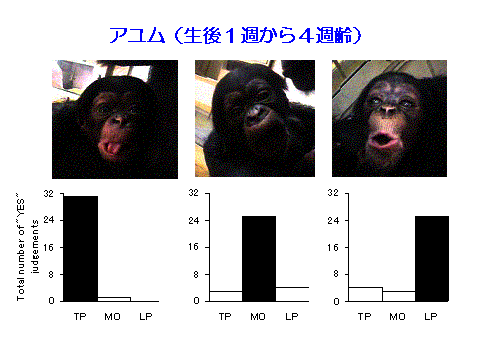- チンパンジーの出産と子育て:見つめあう母子
- 明和(山越)政子(京都大・霊長類研究所)
- 現在、京都大学霊長類研究所では、「チンパンジーの母親が育てたチンパンジーの子どもの認知発達研究」プロジェクトを進めている。2000年4月から8月にかけて、研究所では3個体のチンパンジー、アイ、クロエ、パンが相次いで出産した。彼女たちはそれぞれに独自の知識や技術を身につけている。アイの子どもはアユム、クロエの子どもはクレオ、パンの子どもはパル、と名づけられた。子どもたちは、母親らがおぼえた文字や数字を扱う知識を、いつ、どのように受け継いでいくのか。そうした「知識や技術の世代間伝播」に関する研究の進展が期待されている(松沢,2001)。
- 本シンポジウムでは、ヒトの「出産」という出来事を、進化史的な観点からとらえるため、彼女らの「妊娠・出産・子育て」にまつわる経緯を紹介した。また、「母子間のコミュニケーション」に焦点をあて、チンパンジーの母子関係が、出産以降、どのように築かれていくのかを考察した。
-
- 子育て」は、遺伝的に組み込まれているだけものではなく、生後の学習が大きく関与する。飼育下のチンパンジーは、約2例に1例が育児拒否をする。その理由は、彼らが、他個体の子育てを観察する経験が限られてしまうためだといわれている。アイたちも例外ではなく、子育てというものを観察したことがほとんどなかった。そこで、妊娠期間中から子育てを教えるため、1)野生チンパンジーの子育てのようすをビデオでみせる、2)テナガザルやニホンザルの子どもをヒトの養育者が抱いてみせる、3)チンパンジーのぬいぐるみを実際に抱かせてみる、といった3つの試みが始められた(図1)。

- 図1 表情模倣の実験風景。実験者は、チンパンジー母子と同じ実験室に入り、実験をおこなう。実験者は、記録のための小型CCDカメラをもって、子どもに口の開閉を呈示する(撮影:ナンシー・エンスリン、読売新聞社提供)
- アイたちの妊娠から出産までの経緯は三者三様であり、それぞれにいくつかの問題を抱えていた。しかし幸いにも、彼女たちは問題を乗り越え、個性的なやりかたで子育てをおこなっていった。
- 例えば、アイは、ぬいぐるみを抱く訓練では、あまりうまく抱くことができなかった。しかし、出産後は誰から教えられることもなく、自らアユムを胸に抱いた。
また、仮死状態で生まれてきたアユムの口に指を入れて、自発呼吸を促す行動も観察された。以来3ヶ月間、アイは、
片時もアユムを身体から離すことはなかった。
- 一方、クロエは、出産前から熱心にぬいぐるみを抱き、離さずにいた。しかし、出産後は、産まれおちたクレオから遠ざかり、大事にしていたぬいぐるみのほうを抱いてしまった。
翌日から、友永雅己先生がクロエのいる部屋にクレオを連れて入り、子どもを抱かせるよう試みた。クロエは、目の前にいる小さな生き物に強い興味は示すものの、遠くから眺めては近づき、少し触れてみる、といった行動を繰り返していた。しばらくして、クロエがクレオに近づいたとき、クレオがギャッと声をあげて泣いた。その瞬間、クロエはとっさにクレオを抱きあげた。それ以来、クロエはクレオを片時も離さず抱くようになった。しかし、
その後、クロエは授乳を頻繁に拒否するようになり、新たな問題を抱えながらの子育てが始まった。
- パンは、出産後、パルを手で受けとめたものの、胸に抱くことなく、そのままゆっくりとパルを床においてしまった。そして、パルに
添い寝をしはじめた。パルがもがいて泣くと、パンは、乳首をくわえさせるかわりに、指を口に含ませて泣き止ませるようになった。こうした状態では授乳が不可能なため、田中正之先生が、パンの手をとってパルを
胸に抱くよう指導を続けた。出産後3日目に、パンはようやくパルを胸に抱くようになり、授乳をすることができた。
- 私たちの研究グループは、産後1週目より、チンパンジーの認知発達に関する実験を開始した。チンパンジー母子と研究者の3者が同室しておこなう「参与観察研究」という新しいパラダイムである。チンパンジーの母親たちは、研究のパートナーとして長年かかわってきたそれぞれの研究者と、互いに深い信頼関係を築いてきた。アイは、松沢哲郎先生、クロエは友永先生、パンは田中先生が、長年研究の対象として関わってきた。そのため、彼女たちは、研究者らが子どもたちに直接触れることを、生後すぐから許してくれた。おかげで、私たちは、チンパンジーの新生児期における認知能力を、対面場面で調べることが可能となった(図2)。


- 図2 母親にたいする育児訓練のようす。野生チンパンジーの子育てのようすを撮影したビデオを見せる(右)。ぬいぐるみを使って、実際に抱かせてみる(左・撮影:平田明浩、提供毎日新聞社提供)
- これまで、数多くの知見が得られてきた。それらによると、チンパンジーの新生児には、ヒトの新生児と同様の高い認知能力が生まれながらに備わっている可能性が示唆されている。たとえば、チンパンジーは生後1週齢の時点ですでに、自分では見ることのできない部位である顔を使った3種類の表情(舌突き出し・口の開閉・唇の突き出し)を区別し、模倣できることがわかった(松沢哲郎・友永雅己・田中正之先生との共同研究・図3)。また、生後3週齢には、母親の顔を他のチンパンジーの顔と区別し、母親の顔をより好んで見ることもわかった(友永雅己・山口真美先生[中央大学]との共同研究・図4)。
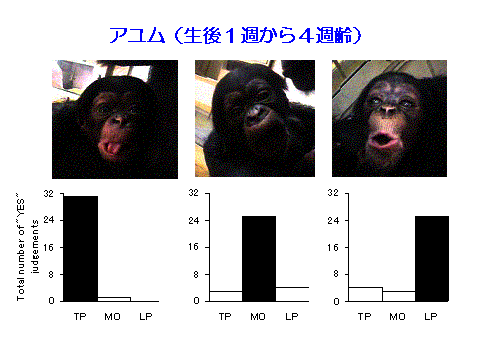
- 図3 チンパンジーの子どもにおける生後1週から4週齢までの、新生児模倣(アユム)。舌出し(TP)、口の開閉(MO)、唇の突き出し(LP)、いずれの表情においても、子どもは模倣した、と評定された。


- 図4 母親の顔の認識の実験風景。実験者は、チンパンジーの子どもに、母親の顔の写真を呈示する(左)。写真は、記録のための小型CCDカメラの上部に取り付けてある。写真をゆっくりと左右に動かし、子どもがどのくらい写真を追視するかを調べた(右)。生後3週齢から、母親の顔写真を、他のチンパンジーの写真より好んで追視するようになった。
- これらの結果は、チンパンジーの新生児が、他者、とくに母親の顔にたいして非常に敏感に反応することを示している。一般に、ヒト以外の動物にとって、他者の顔(目)を見つめることは、攻撃的な意味合いをもつと考えられている。しかし、チンパンジーは、出産後すぐに、母子間で「見つめあう」行動がみられることがわかってきた。子どものまなざしは、対面する母親の注意をひきつけ、働きかけられる機会を増やす。母親からの働きかけは、子どもの活動をさらに強化し、両者のコミュニケーションはいっそう広がりをみせる。ヒトやチンパンジーの母子間のみつめあいには、こうした適応的な意義が存在すると考えられる。
- 「見つめあう」コミュニケーションは、ヒトとチンパンジーに共通する、母子関係の特徴であるらしい。ヒトを含む大型類人猿は、他者と複雑な社会的関係を築きながら生存している(Byrne
& Whiten, 1988)。ヒトやチンパンジーは、生まれながらにして、まずは母子関係という最小単位の枠のなかでコミュニケーションをおこなう社会的動物であるといえるだろう。
- <文献>
Byrne, R. W., & Whiten, A. (1988) Machiavellian Intelligence. Clarendon Press.
松沢哲郎(2001)おかあさんになったアイ 講談社.
- <付記>
今回紹介する研究プロジェクトは、京都大学霊長類研究所の松沢哲郎、友永雅己、田中正之先生との共同研究です。プロジェクトの推進にあたっては、文部科学省・特別推進研究(代表・松沢哲郎、課題番号12002019)、COE形成基礎(代表・竹中修、課題番号10CE2005)の助成を受けました。また、チンパンジーの妊娠期間中の子育て教育は、道家千聡さんを主たる研究者とした共同研究としておこなわれました。本シンポジウムにおいて、内容に関する発表のご許可をいただきましたことを、深く感謝いたします。
公開シンポジウムのページに戻る